
1670年、封建制度の真っ只中に 備前岡山藩主、池田光政の手により 庶民のため(藩士のためではないところがミソ)に設けれた、日本最古(世界最古との説もある)の学校がありました。閑谷学校の存在は、古くは遣唐使であり右大臣ともなった吉備真備、浄土宗の開祖法然、臨済宗の開祖栄西などを、江戸後期には滴塾を催した緒方洪庵や宇田川玄髄、明治以後には日本現代物理学の父といわれる仁科芳雄、日本の社会福祉の先駆者である留岡幸助などなど幾多の文化・教育人を輩出した岡山の文化的気風の一つの結実のようにも思われます。また、明治初期には河合継之助に多大な影響を与えたといわれる備中高梁の偉人、山田方谷が教鞭を執ったこともあるとのことです。
建造物と空間の配置、木・漆・漆喰・備前焼瓦・石の組合せの調和が素晴らしく、建築物としての価値も超一級品で必見の価値があります。また、敷地内には梅林と2本の大きな楷の木があり、春の梅とともに、秋の紅葉が見ものだそうです。
(前記の総ての人物が閑谷学校で学んだわけではありません。)
 |
【講堂〔国宝〕 と小斎(しょうさい)〔重文〕】 総数約23,000枚に及ぶ備前焼の本瓦葺屋根の講堂。内部は10本の欅の円柱と板敷き床という簡素な造りではあるが、拭漆仕上げの柱や床は磨き上げられていて光沢が美しい。花頭窓が一層の美しさを醸しだしている。当時の庶民学校といえば"寺子屋"を思い出してしまうが、ここは現代の教育施設に比べても異次元の荘厳さを持っている。教育はこうした環境でなされるのが理想なのでは・・・と思う。 小斎(画面左の小さい建物)は藩主が訪れた際に使用される建物とのこと。その簡素な造りが結構魅力的に感じる。 |
||||||||
|
|||||||||
 |
【聖廟〔重文〕と2本の楷の木】 聖廟は儒学の殿堂の中心をなす建物。閑谷学校のなかでは最も古い建物です。画面中央に見えているのは外門。 訪れた時期は2月中旬で楷の木はまだ冬姿ですが、秋の紅葉が美しく華麗、とパンフレットにありました。 |
||||||||
|
|||||||||
 |
【校門(鶴鳴門)〔重文〕】 閑谷学校の正門です。屋根は備前焼本瓦葺きで鯱を戴き、この写真では見えませんが、門の両袖の付属屋には花頭窓を備え、門の入口は上部の隅を丸めた優美な形をしています。学校の門としては相当に豪華な造りです。この門を潜った生徒(と言ったかどうか)はそれだけで身の引き締まる思いであったろうと想像できます。ただ残念なことに、この門を通り抜けることはできませんでした。 |
||||||||
【泮池(はんち)と石橋〔重文〕】 校門(鶴鳴門)の手前に幅7メートル、長さ100mを超える泮池があり、校門に向かって石橋が架けられています。「中国上代の諸候の学校である頖宮(はんきゅう)の制に擬してつくられたもの」と説明書きがありました。この重文の石橋の上を歩いて渡って学校に向かいます。 池には鴨様の鳥が我が物顔でゆったりと浮かんでいました。 |
 |
||||||||
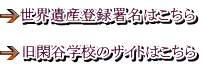
備前市では、『旧閑谷学校は、我が国最初の庶民教育を行うための学校であり、世界に誇れる貴重な教育文化遺産』(「旧閑谷学校の世界遺産登録を求める要望書」より)として、世界遺産登録の署名活動を行っています。興味のある方は右のリンクからどうぞ。